YKT株式会社はものづくりのための各種機器の輸出入販売を事業としており、主に国内のメーカーが製品を製造する際に必要な機器を、欧米から輸入して販売している。同社が販売する機器は高額なものが多く、何度もテストを重ね、納入までに数年を要することもあるという。同社社員は、お客さまとなる国内のメーカーと、機器を製造する欧米のメーカーの橋渡し役を務める。
「当社の仕事は、単に機器を販売するだけでなく、輸入した機器を設置して稼働するまで責任を持って担当するほか、販売後のメンテナンスや簡単な修理なども行います。そのため当社の社員は、機械をはじめとする工学全般の知識が必要になります。また、仕入れ先である欧米の機器メーカーともやりとりするので、英語でコミュニケーションが取れなくてはなりません。幅広い知識と高いスキルが必要な仕事です」(杉山氏)。
 総務部 総務課
総務部 総務課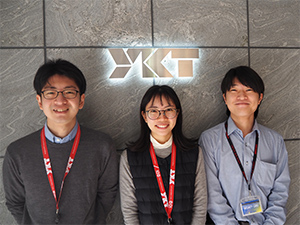 2024年度に入社した新入社員の方々
2024年度に入社した新入社員の方々
2024年度に入社した新入社員の方々
2024年度に入社した新入社員の方々
機械関連の知識や技術が欠かせない同社業務だが、新入社員のほとんどは文系出身者であるという。
「当社の業種は商社や卸売業に分類されるため、新卒採用を行う際は、理系の学生よりも、語学を活かして仕事をしたいという文系の学生が多く集まります。理系の学生は、ものづくりができるメーカーへの就職を志す傾向が強いようで、ここ数年で採用した新入社員はほとんどが文系出身です」(杉山氏)。
そこで同社では、2023年度より文系出身の新入社員が現場に入っても困らないよう、教育体系を再検討。1年にわたり工学の基礎を一から学ぶプログラムに変更した。
「以前は、ある程度研修を行ったら、あとは現場で覚えるというスタイルでした。しかし、当社の業務は専門性が高いので、知識のないままお客さまのもとに伺うと、先方が戸惑うだけでなく、本人も苦しい思いをすることになる。場合によってはお客さまの信用にもかかわります。そこで、配属前に工学系の必要最低限の知識は身に付けられるようにしよう、配属後の現場でお客さまや先輩社員が話している内容が理解できるくらいにはしようということで、私の上司である経営本部長が新たな教育研修プログラムを作成しました」(杉山氏)。
1年に及ぶ新入社員研修は、社内で行うもの、社外で行うものなど多種多様なプログラムが用意されている。そのなかに、JQA計測セミナー『測定技術の基礎(現場長さ測定器編)』と『はじめての計測器管理と取り扱い』の2つの講座が組み込まれている。
これまで2023年度5名、2024年度5名の計10名の新入社員にご受講いただいた。
ちなみに同社と当機構のかかわりはほかにもあり、約15年前から同社が機器の修理等に使用する角度計やブロックゲージなどの校正を当機構にご依頼いただいている。
「校正をお願いしているいないにかかわらず、JQAは業界内でネームバリューがあるので、計測や校正等について学ぶ上でJQAのセミナーなら間違いないだろうと思い、受講を決めました」(杉山氏)。
また、セミナーでの理解を深めるため、事前に統計学の基礎を学ぶ講習を社内で開催。新入社員へのフォローも欠かさない。受講の成果をお聞きした。
「JQAのセミナーは理論と実践の両方が学べるとして好評です。例えば、ノギスの使い方などは今後現場で機械の修理をする際にも必ず役に立つでしょう。また、当社は測定機器も扱っており、お客さまに代わって校正の下準備などを行うこともあります。その際、“校正って何?”では困るので、セミナーを通じて、校正の重要性を知り、校正の流れをイメージできるようになったことは大きいと思います。今後も引き続き新入社員に受講させたいと考えています」(杉山氏)。
2024年度に新卒で入社され、新入社員研修でJQA計測セミナーを受講された方々に、セミナーの印象などをお聞きした。
経営学部出身ですが、1年という長い研修期間を設けていただいたおかげで、工学の基礎的な知識をある程度学ぶことができました。JQAのセミナーは、八王子にあるJQAの事業所まで出向いて受講しました。測定や校正に関して馴染みがなかったので少し不安でしたが、分かりやすいテキストが用意され、それに沿って教えていただきました。全てを理解できたとは言えませんが、計測器や測定方法、校正などについての概要はつかめたように思います。
 電子機器部 電子機器課
電子機器部 電子機器課
鷺 寛彦 氏
 電子機器部 電子機器課
電子機器部 電子機器課
杉浦 真菜 氏
電子機器部 電子機器課
杉浦 真菜 氏
研修中、JQAのセミナーは2回受講しました。1回目のセミナーで初めてノギスや測長器に触れて、その測り方や測る目的などを教わり、2回目で測定器の適切な管理方法などを教わったことがとても良かったです。配属された部署では測長器などを販売するケースもあるので、学んだことが直接役立つ機会もあると思います。その一方で、不確かさなど統計的な内容は私には少し難しく、きちんと理解できなかったところもあるので、今後さらに勉強していかないといけないと思っています。
JQAのセミナーで測定の基礎を学び、実際にいろいろなものを測ってみることで、どういう形状のものが測りにくいのかなどが分かり、当社で取り扱っている三次元測定器などの存在意義を理解することができました。また、研修の一環として、当社が参加する展示会で新入社員が水準器やピンゲージをお客さまに紹介した際も、セミナーを受講していたおかげで、測定時のお悩みごとや校正についてお客さまとスムーズにお話することができ、今後の自信につながりました。
 電子企画・開発部 プロダクト開発課
電子企画・開発部 プロダクト開発課
小島 駿 氏